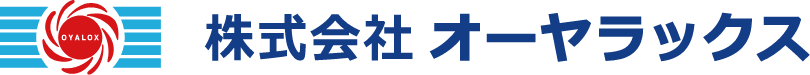記事公開日
最終更新日
食中毒予防のための衛生管理と水質対策の強化を
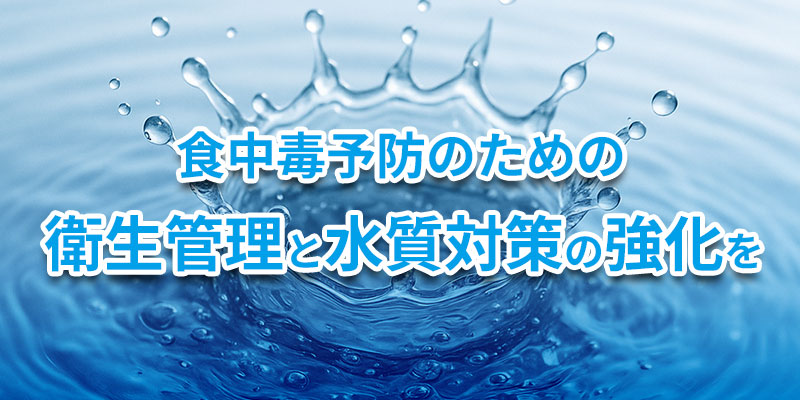
湧き水・井戸水を使用する施設の皆さまへ
食中毒予防のための衛生管理と水質対策の強化を
令和7年10月17日、厚生労働省は「湧き水又は井戸水を飲用に適する水として使用する施設」に向けて、衛生管理の徹底を求める通達(健生食監発1017第1号)を発出しました。
背景には、同年8月に湧き水を水源とした施設で発生した2件の食中毒事案があり、水質管理・殺菌処理の強化が急務とされています。

湧き水は自然の恵みとして清らかな印象がありますが、「見た目がきれい=安全」ではない点に注意が必要です。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 地表・動物・気象の影響を受けやすい | 雨水、動物のふん尿、枯れ葉などで微生物汚染が起こりやすい |
| 殺菌処理されていないことが多い | 「天然だから安心」と誤認されるケースも |
| 感染リスクがある | 大腸菌、カンピロバクター、ノロウイルス等の検出例もあり |
特に“沢の湧水(沢水)”のように地表に近く、雨や環境の影響を受けやすい水源では、定期的な水質チェックと殺菌処理が不可欠です。

1. 水源の衛生管理
取水口周辺の清掃・点検
動物や人の侵入を防ぐ柵の設置
枯葉や泥の混入を防ぐ構造の整備
2. 殺菌処理の実施
次亜塩素酸ナトリウム(ピューラックス等)による消毒
推奨残留塩素濃度:0.1~1.0 mg/L
自動注入装置の設置・点検・記録管理
3. 水質検査の強化
年1回以上の法定検査に加え、日常的な確認(色、臭い、濁り、残留塩素)
大雨・災害後の臨時検査の実施
異常時の使用中止と対策の徹底


消毒の有効性を確認するには、残留塩素の測定が不可欠です。
DPD試薬を使って、遊離残留塩素と反応 → 赤く発色
残留塩素計で濃度を確認
HACCP対応のためにも記録を習慣化することが推奨されています

| 項目 | 実施内容 | 頻度 |
|---|---|---|
| 水源点検 | 井戸・湧き水の構造や衛生状態を確認 | 月1回以上 |
| 殺菌装置点検 | 薬剤の補充、注入濃度のチェック | 週1回以上 |
| 残留塩素測定 | DPD法による測定と記録 | 毎日または使用前 |
| 水質検査 | 専門機関による分析 | 年1回以上+臨時 |
| 記録保存 | 水質・殺菌管理の履歴を保存 | 常時/HACCP対応 |


ピューラックスなど適切な殺菌剤を正しい濃度で使用する

残留塩素をDPD法などで定期測定し、記録を残す

異常があればただちに水の使用を中止し、水質検査を実施する
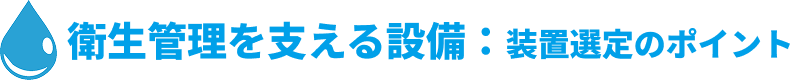
湧き水・井戸水を安全に活用するには、次亜塩素酸ナトリウムの注入装置や残留塩素測定の導入が重要です。
▷ 実績のある装置例
オーヤラックスの滅菌装置では以下のような装置がございます
※機器の選定は、水源の種類・水質・使用量などを踏まえて検討する必要があります。導入をご検討の際は、オーヤラックスまでご相談ください。